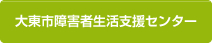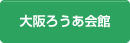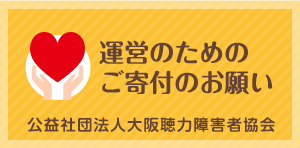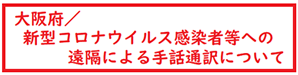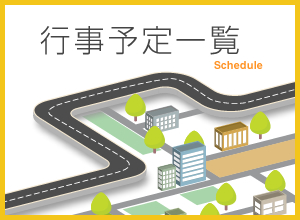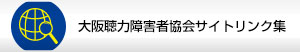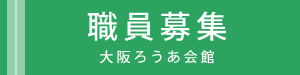公益社団法人大阪聴力障害者協会 定款(2023年6月25日改訂)
情報公開
選挙に関する規則
入退会及び会費等に関する規則
役員旅費支給規則
| 年 度 |
月日 |
できごと |
| 1915年(大正4年) |
11月25日 |
日本聾唖協会創立(京都にて。初代会長 小西信八) |
| 1917年(大正6年) |
2月11日 |
本会創立(日本聾唖協会大阪支部)
創立者は福島彦次郎ほか4名。当時の会員数は33名。
初代会長 宮島茂次郎。事務所は大阪市立盲唖学校 |
| 1920年(大正9年) |
4月2日 |
第3回日本聾唖協会総会を大阪で開催。
全国から約200名集結 |
| 1928年(昭和3年) |
1月 |
全国で初めての、ろうあ者を主体とする劇団「車座」が大阪で発足 |
|
4月2日 |
第1回全国ろうあ陸上競技大会を、大阪府立生野中学校グラウンドで開催。大阪が初優勝 |
|
4月3日 |
第3回社団法人日本聾唖協会総会を大阪で開催 |
|
9月23日 |
「車座」が大阪朝日会館で「父帰る」を初公演 |
| 1940年(昭和15年) |
8月2日 |
第16回全国ろうあ陸上競技大会を大阪市港区運動場で開催。
大阪が2度目の優勝 |
| 1942年(昭和17年) |
5月1日 |
第2次世界大戦による戦時政策として、社団法人日本聾唖協会は日本聾唖福祉協会に吸収され、大阪支部の組織と活動も停止 |
| 1947年(昭和22年) |
4月1日 |
大阪聾唖協会を復活総会。
福島一俊、谷口勝、谷口久子、大家善一郎などの奔走によって80名参集。大阪市立聾学校野江仮校舎で開催。会長 福島一俊 |
| 1948年(昭和23年) |
5月24日 |
群馬県伊香保温泉で全日本聾唖連盟結成。
初代連盟長に大阪聾唖協会顧問、藤本敏文を選出 |
| 1949年(昭和24年) |
4月18日 |
近畿聾唖連盟結成。大阪で結成総会 |
| 1950年(昭和25年) |
6月3日 |
社団法人認可を取得、「社団法人大阪ろうあ協会」発足。 |
| 1955年(昭和30年) |
5月1日
~5日 |
大阪で全国ろうあ者大会を開催。参加者2500人
会場は中之島中央公会堂 |
| 1960年(昭和35年) |
9月18日 |
天皇奨励金下賜ならびに法人認可10周年記念祝賀会を大阪市立ろう学校講堂にて開催。参加者450名 |
| 1963年(昭和38年) |
5月3日 |
大阪府から団体社会事業功労賞として表彰状と金一封を受け取る |
|
9月21日
~22日 |
住之江球場にて、第9回全国ろうあ者野球大会を開催。
大阪チーム初優勝 |
| 1965年(昭和40年) |
3月21日 |
大阪ろうあ協会青年部結成
大阪市立ろう学校にて、第1回青年ろう者大会開催。参加者500名
ろうあ青年と大阪学芸大学との交流会 |
|
4月21日 |
藤本敏文が会長を引退し名誉会長になる。
2代目会長に大家善一郎 |
| 1966年(昭和41年) |
|
「手話の会」発足 |
|
2月10日 |
第1回障害者の対大阪府交渉 参加者500名 |
| 1967年(昭和42年) |
10月28日 |
「ろう者の生活と権利を守る会」(守る会)結成 |
| 1969年(昭和44年) |
7月1日 |
大阪府ろうあ者福祉指導員制度開始 |
| 1970年(昭和45年) |
3月25日 |
大阪ろうあ協会と守る会を中心に「ろうあ会館建設実行委員会」発足 |
| 1973年(昭和48年) |
9月24日 |
第1回全大阪ろうあ者文化祭を大阪市立教育青年センターで開く |
| 1977年(昭和52年) |
4月20日 |
大阪ろうあ会館オープン
大阪としての手話通訳派遣制度実現 |
| 1982年(昭和57年) |
7月4日 |
臨時総会開催「大阪ろうあ協会」から「大阪聴力障害者協会」へ改称
3代目会長に揖野昭夫が就任。会員数1000人 |
| 1985年(昭和60年) |
8月23日 |
「アイラブコミュニケーション」パンフレット120万部普及運動開始
大阪の目標は10万部 |
| 1987年(昭和62年) |
3月31日 |
「アイラブコミュニケーション」パンフレット10万部突破集結集会 |
| 1988年(昭和63年) |
1月21日 |
3代目会長揖野昭夫逝去(享年59歳) |
|
2月12日 |
故揖野昭夫の協会葬を行う |
|
4月24日 |
4代目会長に清田廣就任 |
| 1990年(平成2年) |
6月15日 |
熊取町に「なかまの里」建設用地確保
1億5千万円募金運動スタート |
| 1993年(平成5年) |
1月19日 |
「社会福祉法人大阪聴力障害者協会福祉事業協会」結成 |
| 1994年(平成6年) |
5月8日 |
重度重複聴覚障害者の生活・労働施設「なかまの里」開所
総工費9億2千万円 |
| 2000年(平成12年) |
|
大阪ろうあ会館で介護保険事業(居宅介護支援、訪問介護)がスタート |
|
10月 |
大阪ろうあ会館出張所・守口障害者生活支援事業所として「京阪地区聴力障害者センター みみ」が開所 |
| 2001年(平成13年) |
|
ろうあ老人ホーム・重度重複聴覚障害者通所施設建設特別決議
5億円募金運動スタート |
| 2014年(平成26年) |
4月 |
公益社団法人 大阪聴力障害者協会として公益社団法人格取得 |
|
|
|
|
公益社団法人 大阪聴力障害者協会(大聴協)は、大阪に住んでいる聴力障害者のための最大の団体です。
また、大阪でただ一つ、府の認可を受けて法務局に登録された公益法人です。
1965(昭和40年)ごろまで、聴力障害者(ろうあ者)は、誤解され、差別され、社会で通じない口話と手話への偏見に苦しんできました。大企業への就職差別・賃金差別、自動車の運転免許や銀行ローンの拒否……。
それを変えたのは聴力障害者自身の運動です。
大阪では大聴協が、全国的には大聴協の加盟する一般財団法人 全日本ろうあ連盟(全日ろう連)が、社会の差別と偏見を無くし、理解を広げるために運動してきました。
その成果として……、各市の福祉指導員制度や大阪ろうあ会館と手話通訳者の養成・派遣が始まり、また、運転免許試験に補聴器使用が認められ、住 宅ローン拒否の理由となった民法11条が改正され、障害基礎年金が新しく始まり、大企業も就職の門戸を開くようになり、手話が大きく広がり、テレビで手話講座が放映される時代になりました。
大聴協と全日ろう連に集まった聴力障害者の団結と運動の成果です。
聴力障害者の平等と福祉充実は、聴力障害者が一つに集まった力によって前進します。
大阪のすべての聴力障害者が大聴協に入会し、全日ろう連を通じて日本全国の聴力障害者と力をあわせ、そして世界ろう連盟(WFD)を通じて世界のすべての聴力障害者と交流し、運動してゆきましょう。